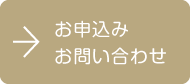10月25日に開催された敬心学園第22回職業教育研究集会の全体にて、弊社取締役員芳川玲子が講演をしました。
およそ90分の講演の中で、配慮が必要な学生や支援を必要とする人との関わりを考えるうえで、非常に示唆に富む内容であったと好評を頂きました。
講演の概要は次の通りです。
テーマ 非認知スキルの向上に向けてー配慮が必要な人とのコミュニケーションを高めるためにもー
🔹非認知スキルとは?
「非認知スキル」という言葉、最近よく耳にしますね。
学力や知識のようにテストで測れないけれど、人の成長や社会的な成功を支える力。
たとえば──
・自分の気持ちを理解し、落ち着かせる力(自己調整)
・他者の気持ちを感じ取り、関係を築く力(共感・協働)
・失敗から立ち直る力(レジリエンス)
・やり抜く力、そして自分の行動に意味を見出す力(動機づけ)
こうした力は、認知的な能力と対立するものではなく、学びや働き、そして生き方を支える「もう一つの車輪」だと芳川は語ります。
🔹現代の学生が抱える課題
芳川が示した調査では、専門学校の学生たちが抱える課題として、
・経済的な不安や生活との両立
・学習意欲や継続力の低下
・自己理解の浅さ、感情コントロールの難しさ
などが挙げられていました。
「怒られ慣れていない」「反省よりも防御に走る」「失敗を人に話せない」──。
こうした背景の中で、自己認識や自己調整といった非認知スキルが育ちにくくなっているのだそうです。
🔹支援の第一歩は「気づき」から
繰り返し強調していたのは、「感情に気づくことが学びの出発点」ということ。
たとえば、授業や実習のあとに振り返るとき、いきなり「どうすればよかった?」と問うのではなく、
「そのとき、どんな気持ちだった?」と尋ねてみる。
それを「天気」や「色」で表現してもOK。
「今日の気分は晴れ?くもり?それとも小雨?」
そんな対話の中に、自己理解の芽が生まれます。
🔹教員・支援者ができること
非認知スキルを育てるうえで、教員や支援者に求められるのは「技術」ではなく「関わりの姿勢」です。
芳川は次のような原則を挙げていました。
1.否定しない
2.選択肢を与える
3.一貫した対応をする
4.感情のモデルを見せる
「できなかったね」ではなく「どこまでできた?」
「やる?」ではなく「AとB、どちらにする?」
小さな安心の積み重ねが、“もう一度やってみよう”という力を育てます。
🔹「強みを語る」ことで動機づけが生まれる
非認知スキルを育てるもう一つのカギは、「語り」だと芳川は言います。
学生が「できたこと」や「うまくいった瞬間」を言葉にすることで、自分の強みや成長に気づける。
その経験が、“自分で選び取る学び”へと変わっていくのです。
🔹おわりに
非認知スキルは、“優しさ”や“人間性”という抽象的なものではなく、教育によって育てることができる「力」です。
そして、それを育てるには、まず私たち自身が「整える」「気づく」「意味づける」ことから始める必要があります。
支援する側も、学ぶ側も、“心のスキル”を共に磨いていく。
そんな学びの場が広がっていくことを願っています。