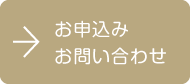(2025.3.9記) 【セミナー概要】
2月22日(土)に開催されたセミナー「安心できない子どもの理解と支援」の概要版です。
児童自立支援施設での経験
「安心できない子どもの理解と支援」をテーマにした講演の中で、川村先生は自身の経歴と児童自立支援施設での経験について語った。
先生は横浜市の中学校教員や生徒指導専任を経て、児童自立支援施設「桜坂分校」の開設に携わり、現在は横浜市子ども家庭支援課で子どもの権利擁護を担当している。
児童自立支援施設は、不良行為や家庭環境の問題を抱える児童を支援する施設であり、児童相談所や家庭裁判所の判断を経て入所が決定される仕組みについて説明があった。
子どもの安心と愛着の重要性
安心できない子どもの特徴として、仲間への思い入れの少なさ、人間関係の希薄さ、集団行動の困難さなどが挙げられた。
具体的な事例として、虐待を受けた中学3年生の男子生徒や、非行に走った生徒のケースが紹介された。
また、愛着理論に基づき、子どもたちが「今だけを生きる時間感覚」に陥りやすいことや、過去・現在・未来をつなぐ振り返りプログラムの重要性が説明された。
さらに、DSM-5における愛着障害の分類や、学校における子どもたちの安心度を測る「逆三角形モデル」も紹介された。
虐待・不適切な養育を受けた子どもへの支援
虐待や不適切な養育を受けた子どもたちの支援について、以下の主要なポイントが示された。
- 安心・安全な環境づくりが最も重要であること
- 子どもの成長には時間がかかり、一筋縄ではいかないこと
- 愛着の問題を抱える子どもは言葉の発達が不十分であることが多く、行動と言葉の一致を図る必要があること
また、学校組織においては、教職員が安心して働ける環境の整備や、情報共有の仕組みづくりが支援の基盤となることが強調された。